お風呂にて。
私「サイン・コサインって聞いたことある?」
長男「ええと、うん、聞いたことはある。タンジェント?」
私「そう、サイン・コサイン・タンジェント。たとえばここに、一メートルの針があるとする」
長男「ふんふん」
私「ないよ!」
長男「え?」
私「一メートルの針なんてない。ごめん。言い間違い。一メートルの棒があるとする」
長男「なんだよ、それ」
私「まあいいから。で、その棒の片方を固定して、コンパスみたいにぐるりんこんと回すとしよう。ここだとタイルの壁の上だから、棒を壁に沿わせて縦に回すことになるけれど」
長男「ふんふん」
私「そのとき、棒の端っこは円を描くね」
長男「そうだね」
私「最初角度がゼロ度のとき、端の高さは0だ」
長男「うん」
私「で、90度のとき、端の高さは1になる。0度から90度まで動かしていくと、高さはだんだん高くなっていく」
長男「はいはい」
私「このとき、角度から高さを求める関数がサインになる」
長男「へえ、そうなんだ」
私「90度を越して、180度まで動かしていくと、高さはだんだん低くなる」
長男「そうだね」
私「では問題。0度から180度まででサインが一番大きくなるときの角度は?」
長男「それは90度」
私「はい正解。ではサインが一番小さくなるのは?」
長男「0度と180度」
私「よしよし、よく180度忘れなかったね」
長男「へへっ」
私「サインが高さ――つまりY軸への影だとすると、X軸への影がコサインになる」
長男「ふうん」
私「0度のときコサインは1になる。そして90度に向かうときコサインは1からだんだん0に減っていく」
長男「はじめはゆっくり減って後から速く減るね」
私「そうそう!よくわかるね。そして…90度を越すと今度はコサインはマイナスになる。180度のとき、コサインは-1になる」
長男「ははあ、なるほど」
私「さっき、0度から180度の範囲ではサインは0以上だったけれど、180度を越すと今度はサインがマイナスになる」
長男「あっ、わかったわかった。あのね、サイン・コサインの順でいうとここ(第一象限を指さす)がプラス・プラスでしょ」
私「そうだね」
長男「そしてここがプラス・マイナス、こっちがマイナス・マイナス。そしてここがマイナス・プラスだ」
私「そのとおり!すごいまとめだ!」
長男「へへへ」
私「棒をぐるぐる回したとき、Y軸への影はこんな風に振動し、X軸の影も振動する。少しずれているけれど、実は振動の様子は同じだ。わかりにくいから別のグラフにして、こんなふうに描いたもの、これがサイン・カーブになる」
長男「ふうん」
私「音叉ってあるでしょ?ポーン、という音を出したとき、その波形はサイン・カーブになる」
長男「あ、そうなんだ」
私「小学校では0度から360度のように角度を表すけれど、もう少しするとラジアンという角度の表し方を習うよ」
長男「ラジアン?」
私「そう。ラジアン。0度は0ラジアン。180度はπ(パイ)ラジアン。つまりだいたい3.14ラジアンだね」
長男「え、えええ?さっぱりわからん」
私「単なる比例だよ。360度になると2πラジアン」
長男「6.28ってこと?」
私「そうだね」
長男「なにそれ」
私「半径1の円の円周の長さは?」
長男「え?――6.28だね」
私「そう。2πになるよね。この円周に相当する角度がちょうど2πラジアンなんだ」
長男「?」
私「円周の半分の弧の長さはπだ。この円弧に相当する角度がちょうどπラジアン。つまり、ラジアンは、半径が1の円の「円弧の長さ」を使って「その円弧に対応する角度」を表しているんだよ」
長男「ほほう…」
私「度をラジアンに変換するのは簡単だ。360で割って2πを掛ければよい」
長男「6.28×角度÷360でもいいよね」
私「もちろん。逆にラジアンを度に変換するのも楽。2πで割って360を掛ければOK」
長男「ふんふん」
※追記:数学で半径をrとおくのは、radian(ラジアン)から来たのではなくradius(半径)から来たのだと思います(少なくとも直接は) > メールくださった方へ。
※追記:id:okamoto7さんから、比であることを明示したほうがよいという主旨のコメントをいただきました。ありがとうございます。上の会話では「ラジアンが長さを長さで割った無次元量になっている」ことが明確になっていないのですね(リアル会話なのでしょうがないといえばしょうがないですが(^_^;)。
「ラジアンは(円弧の長さ)÷(半径の長さ)という量を使って角度を表している」ということです。
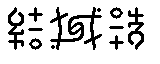


![[ギコ猫と暗号技術入門]](https://www.hyuki.com/cr/crcat.gif)
![[icon]](https://img.hyuki.net/20220619121014-abd58cfc2ab436f4.png)